お寺に足を運ぶ機会がある方は、一度は目にしたことがある 単語
ご真言(ごしんごん)
しかしながら、意味やなんで唱えるのか知らない方多いと思います。そこで今回のブログでは、真髄とまではいかなくとも、ご真言ってそんな感じなんだぁと知れるような内容で解説していこうと思います。

知って自分の心の支えになったりますよ。まずは知ってみましょうね
ご真言ってなぁに?
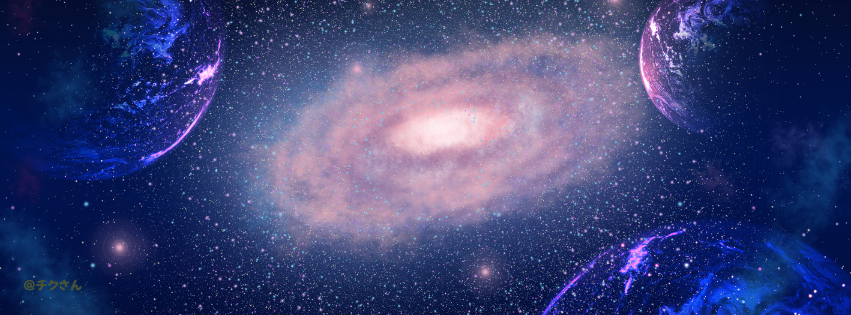
ご真言(ごしんごん)は、仏教における短い呪文や経文で、特定の仏や菩薩、明王、天などを讃えるために唱えられるものです。サンスクリット語(梵語)で「マントラ」とも呼ばれ、その言葉自体に特別な霊的な力が宿っているとされています。
サンスクリット語と漢訳
ご真言が「真実の言葉」とされるのは、サンスクリット語の「mantra(マントラ)」が“真理の言葉”という意味を持ち、漢訳で「真言」とされたことに由来すると言われています。
特に密教では、「真言=仏の本質や智慧が宿る神聖な音」であり、空海の教えや『大日経』などの古典経典でもそう解釈されています。
ご真言の構成
真言(マントラ)は、古代インドのサンスクリット語に由来し、霊的な力を宿す神聖な言葉として伝えられてきました。日本では「ご真言」とも呼ばれ、特に密教の修法の中で大切に扱われています。
ご真言は、一般的に以下のような三つの要素で構成されていることが多いです。ただし、すべての真言がこの形に当てはまるわけではなく、内容や用途によって構成が異なる場合もあります。それでも、この構造を知っておくことで、ご真言の世界に親しむための第一歩になるでしょう。
開頭句(おん)
多くのご真言は、「おん」という音で始まります。これは、サンスクリット語の「Om(オーム)」に由来するもので、「宇宙の根源的な音」「始まりの音」とされています。
「おん」は、すべての存在を生み出すエネルギーの象徴ともいわれており、唱えることで心が整い、霊的な次元とつながる準備が整うと考えられています。瞑想や祈りの前に心を落ち着かせ、集中力を高める働きもあります。
主要部分(中心句)
ご真言の中心をなす部分です。ここには、特定の仏様や菩薩のお名前、そのご利益や象徴する力をあらわす言葉が含まれています。
たとえば、「ばざら(vajra)」という音は「金剛」を意味し、不動の意志や破壊できない真理の象徴です。他にも、「さとば(svatava)」や「たら(Tārā)」など、仏の性格や功徳を音で表した語が入ることが多く、それぞれに深い意味があります。この部分は真言ごとに大きく異なり、その仏様のエネルギーとつながるための大切な鍵となる部分です。
結尾句(そわか)
多くの真言は「そわか」で締めくくられます。これは、サンスクリット語の「Svāhā(スヴァーハー)」を音写したものです。「そわか」は「どうかこの祈りが届きますように」「この願いが成就しますように」
という意味を持ち、唱えた真言が宇宙に放たれ、成就に向かって動き始めるための【締めの言葉】ともいえます。
日本語にすると少し堅く感じるかもしれませんが、古来より仏に向かって願いを託す、心からの奉納の意が込められています。
どうしてご真言を唱えるの?
ご真言を唱える理由は、実にさまざまです。宗教的・霊的な意義もあれば、日常生活を穏やかにするための実践として唱える人もいます。ここでは、その代表的な理由をいくつかご紹介します。

1. 心の落ち着きと集中
日々の暮らしの中で、気づかないうちに心がざわついたり、不安や焦りを感じたりすることってありますよね。そんな時、ご真言を唱えることで、音の響きとリズムに意識を集中させ、心を静め、気持ちをリセットする効果が期待できます。
これは、いわば「声に出す瞑想」のようなもので、マインドフルネスの一種ともいえます。
たとえば「おん ころころ せんだり まとうぎ そわか」とゆっくり唱えていると、次第に呼吸が整い、思考がシンプルになっていくのを感じられるかもしれませんね。
このご真言は、薬師如来さまのご真言です。正式には「薬師瑠璃光如来真言」 YouTubeにもたくさん動画がありますからね。その中のひとつを掲載しておきます。唱えるのが怖かったとしても少し聞いてみるだけでも心が落ち着くきっかけになるのかなと思いますよ。
2.仏や菩薩とのつながり
ご真言には、特定の仏様や菩薩のお名前、功徳をあらわす言葉が含まれており、その存在とつながるための「音の橋」のような役割を果たします。
たとえば、観音菩薩の真言を唱えるとき、ただ音を出しているのではなく、慈悲のエネルギーと心を通わせている感覚になることもあります。これは、親しい人の名前を呼ぶことで、その人を思い出し、つながりを感じる感覚に近いかもしれませんね。

言霊といわれることに込められたエネルギーはこういったご真言でもあると言えますね。
3.霊的なパワーと加護
ご真言には、古来より「霊的な力が宿る音」としての側面があり、唱えることでそのパワーに守られ、支えられると信じられてきました。
たとえば、観音菩薩の真言は苦しみから救ってくれる慈悲の力を、不動明王の真言は困難に立ち向かう強さや守護力をもたらすとされています。まるで「音のお守り」のように、日々の中で心の拠り所になってくれる存在です。
4. 邪気払いと浄化
特に密教においては、ご真言には場や人のエネルギーを清める力があるとされています。たとえば、不動明王の真言などは、強い浄化力があるとされ、悪い気や災い、マイナスの感情を払いのけるために用いられます。
ネガティブな雰囲気が気になるとき、自分の気持ちがどんよりしているとき、ご真言を唱えることで空気が変わったように感じることもあるかもしれません。それは、内と外のエネルギーを整える効果が働いているからだと信じられています。
5. 自己成長と悟りの道
仏教において、ご真言は単なる音や儀式ではなく、自己を深めるための実践法として大切にされています。修行者は日々の修行の中で真言を唱え続け、心を鍛え、煩悩を静め、真理に近づく努力を重ねています。
これは、まるでアスリートが毎日のトレーニングで体を整えるようなもの。精神の筋トレと言ってもいいかもしれません。何度も繰り返すことで、だんだんと自分の内側にある強さや静けさに気づけるようになっていきます。

僕自身も意味も分からず唱えていた時、アイデンティティがどんどん出てきた時がありましたねぇ
ご真言の果たす役割
- 仏や菩薩の功徳を引き出す ご真言を唱えることで、仏や菩薩の持つ霊力や慈悲が私たちのもとに届きやすくなり、祈願の成就や心の安定に繋がるとされます。
- 心と精神の浄化 真言を繰り返すことで、心が落ち着き、煩悩や邪念が静まり、内側から浄化されていく感覚が得られるでしょう。
- 守護と加持の力 特定のご真言は、災いから身を守るために唱えられることが多く、霊的な守護(=加持)を受ける手段として用いられます。

自分のお守りとしてのひとつの形を心の中にもってみてくださいね。
ご真言を唱える際のNG行動
せっかくご真言を唱えるのなら、その尊さや意味をしっかりと感じながら、良い心持ちと環境で臨みたいものです。ただ唱えれば良いというものではなく、心構えや環境によって、ご真言のもたらす力や自分自身の感じ方も大きく変わってきます。ここでは、ついやってしまいがちなNG行動と、それに対するアドバイスをいくつかご紹介します。
1. 不敬な態度で唱える
ご真言は、仏や菩薩と心を通わせるための神聖な言葉です。だからこそ、冗談半分や軽い気持ちで唱えるのは避けましょう。信仰の深さは人それぞれであっても、「敬う心」を持つことが大切です。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、せめて静かな心持ちと丁寧な気持ちで唱えるように意識してみてください。
2. 急いで唱える
早口でバババッと唱えてしまうと、言葉の一つひとつが雑になってしまい、心が伴わなくなります。真言はリズムや響きそのものがエネルギーを持つとされているため、焦らず、呼吸に合わせて一音一音を丁寧に唱えることがとても大切です。たとえ短時間であっても、ゆっくり丁寧に唱えたほうが、心も整いやすく、効果も実感しやすいと言えますよ。
3. 正しい発音を軽視する
真言はサンスクリット語(梵語)をもとにした音で成り立っています。そのため、音の響きやリズムがとても重要です。発音を間違えると、意味やエネルギーが変わってしまうとも言われています。
身近に教えてくれるお坊さんや指導者がいない場合は、YouTubeなどで信頼できる僧侶や専門家が唱えている動画を参考にするのもおすすめです。繰り返し聞いて、耳で覚えていくのも立派な修行の一つですよ。

僕がいつも聞いているご真言のYouTubeを載せておきますね。
4. 周囲の環境を無視する
できるだけ、静かで清らかな空間で唱えるようにしましょう。テレビの音が流れていたり、スマホの通知が鳴り続けていたりすると、集中が途切れてしまいます。
必ずしも完璧に整った仏間が必要なわけではありませんが、部屋を軽く掃除する、香を焚く、照明を落として静かにするなど、できる範囲で環境を整えてみてください。それだけで、心の中も自然と落ち着いてきます。
5. 心が乱れているまま唱える
怒りや悲しみで心が乱れているときに、無理に真言を唱えても、かえって逆効果になることがあります。特に、「誰かを見返してやる」「呪ってやる」というようなネガティブな気持ちを込めて唱えることは絶対に避けましょう。
ご真言は本来、慈悲や浄化、守護のエネルギーを持つ神聖な言葉です。
そんなときは、まず深呼吸をして気持ちを整える、好きな音楽を聴く、散歩に出てみるなどして、心が少し落ち着いてから唱えるようにしましょう。無理して唱える必要はありません。「今日は唱えない」という選択も、大切な信仰のかたちです。
ご真言を唱える際の注意点
1. 清潔な状態で行う
ご真言を唱える前に、まずは自分自身を整えましょう。手や口を洗い、衣服を軽く整えるだけでも構いません。お風呂に入った後や、朝の身支度を終えたタイミングもおすすめです。
身体を清めることは、自分の心も清らかにする第一歩。外側の清潔さは、内側の意識を整えるための儀式のようなものとも言えます。
また、身の回りの空間もなるべく清潔に保ちましょう。机の上を片付けたり、軽くお香やお線香を焚いて空気を整えるだけでも、気持ちが自然と落ち着いてきます。
2. 心を込めて唱える
ただ口先だけで唱えるのではなく、仏さまや菩薩への感謝や願いを込めて、心を注いで唱えることが大切です。言葉の意味がわからなくても、「心を向けている」という意識があれば、それはきっと伝わるはずです。
忙しい日常の中であっても、短い時間で構いません。ほんの一瞬でも、丁寧に心をこめて唱えることが、ご真言を真に「生かす」方法です。
3. 継続的に唱える
真言の力は、一度唱えたからといってすぐに結果が現れるというものではありません。大切なのは継続すること。たとえ一日に一回でも、毎日少しずつでも唱え続けることで、徐々に心に変化が生まれていきます。
これは、仏さまへの信仰というよりも、自分自身との約束を守る小さな修行のようなものかもしれません。繰り返すことで、心が整い、日常が少しずつ穏やかになっていくのを感じるはずです。
4. 専門家から学ぶ
ご真言には、それぞれに深い意味と背景があります。もし、特定の真言についてもっと深く知りたいと思ったら、お寺の僧侶や信頼できる専門家に相談してみるのも良い方法です。
正しい意味や唱え方を学ぶことで、今までなんとなく唱えていた言葉に重みや奥行きが加わり、実践の質がぐっと深まります。最近では、オンラインで法話や指導を受けられる機会も増えているので、そういったものを活用するのも一つの手ですよ。
まとめ
せっかく、お参りに行ったら掲げられているご真言を唱えないのはもったいないことがご理解いただけましたかね?意味が分からなくても、唱えることでご利益 パワーをもらえるご真言。
ご真言は、特別な知識がなくても、誰でも始められる心の習慣です。けれど、ほんの少しだけ「気をつけるべきポイント」を知っておくと、唱える時間がもっと豊かで意味のあるものになります。
清潔な心と姿勢で、静かな時間の中に自分を置き、感謝と祈りを込めてご真言を唱えてみてください。きっと、日々の中に穏やかな変化が訪れるはずです。
僕自身も毎日たくさん唱えています。家には仏様を祀っておりますので、その仏様のご真言をお供え物を供える際にいつも唱えます。
おかげさまで、生活も安定して家族間で起きていた不安な事もどんどん落ち着いてきました。
読者の皆様にも、たまたまこのブログを読んだ人にもご真言を唱えると起きる日常の変化を体験してほしいなと僕は思います。むやみやたらに唱えるな。危ないぞ。という声も聞きます。確かに唱える時の心持ちが適切でなければ危ないかもしれませんね。しかし、今回のブログに書いた注意点を気にしつつ心穏やかに唱えることが出来れば日々が変化していくと僕は思っております。
お寺に参拝に行った際だったり祀っている仏様のご真言だったりと機会がある時に唱えてみてくださいね。
以上!チクさんブログでしたー!


コメント